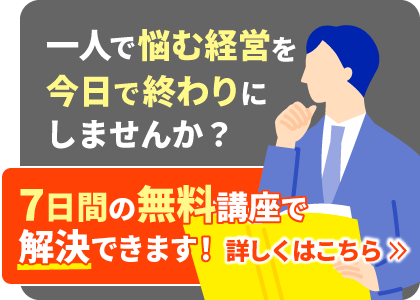ワコール創業者・塚本幸一の生涯から学ぶ“働き方”と経営の本質【書評】
働くということは、こんなにも誇りに満ちている
“働くことって、こんなにも誇りに満ちているんだ”
そんな感動と気づきを与えてくれた一冊をご紹介します。
それが、『ブラジャーで天下をとった男―ワコール創業者 塚本幸一』です。

私は普段、社労士事務所で人事労務に携わりながら、「働くこと」に対するネガティブな印象を少しでも変えたい、ポジティブの輪を広げたい、と日々考えています。この本との出会いは、そんな想いに火をつけてくれました。
戦後の日本経済を支え、活性化させた実業家といえば、
松下幸之助(パナソニック)、出光佐三(出光興産)、稲盛和夫(京セラ・KDDI)、佐治敬三(サントリー)など、今なお語り継がれる名経営者たちがいます。
本書には、まさにそうした“昭和のレジェンド”たちが次々と登場し、読み進めるたびに驚きの連続でした。
「こんなすごい人たちが同じ時代を生き、切磋琢磨しながら日本の復興に力を尽くしていたのか」と、胸が熱くなります。
なかでも驚いたのは、「塚本幸一なしに、“新経営の神様”と呼ばれた稲盛和夫は存在しなかっただろう」と記されていたこと。
つまり、塚本氏はあの稲盛氏にさえ影響を与えた、時代を動かすほどの人物だったのです。
塚本氏の根底にあったのは、「働くことは尊く、会社とは人が輝く場であるべきだ」という信念。
単なる経営ノウハウではなく、「働くとはどういうことか」「労使のあるべき関係とは何か」といった本質的な問いを体現していた方だと感じました。
「和江留」から始まった気づき
この本を読むきっかけは、MiraQのつながりで訪れた、ワコールマニュファクチャリングジャパン長崎雲仙ファクトリーの工場見学。
ふと壁を見たときに「和江留」という文字が目に入り、「ワコールって漢字あるの?!」と驚き調べてみました。
「和江」とは父 粂次郎の雅号であり、出身である江州から「江州に和す」を意味する。また、「長江(揚子江)で契りあった和」としても読め、長江を遡り、中国の歩兵第六◯連隊に配属されたことを社名に込めている――。 (『ブラジャーで天下をとった男―ワコール創業者 塚本幸一』より引用)
そこから彼の生き様をもっと知りたいと思い、本書を手に取りました。
戦争を生き抜いた男が、女性の未来を拓く
「なぜ男性が、女性下着を事業に?」
最初に抱いた疑問の答えは、戦争という過酷な背景にありました。
塚本氏は、あの過酷なインパール作戦の生き残り。命を賭して帰国した彼が見たのは、GHQの管理下で力を失った戦後日本。
「日本を復興させたい。ただそのためには男尊女卑のこの時代を抜け出し、女性が活躍する社会が必要だ」と考えたのです。
最初はネックレスの販売から始まり、そこから女性が身につけるものを広げ、アメリカから下着の情報を取り入れ販売を始めました。全ての行動の軸にあったのは、日本再建と女性のエンパワーメントです。
信頼から始まる経営——
読んでいて「ぶっ飛びすぎやろ…!」と思ったのが、「相互信頼の経営」を本気で貫いた塚本氏の姿勢です。
社員数が増え、一般的には労使トラブルや管理の煩雑さから“規則強化”に走る企業が多くなる中、彼はむしろその逆を行くのです。
「ワコールの社員を本当に信頼しているのなら、今のような規則は必要なのか?
世間一般のルールをそのまま持ち込んでも、“世間並み”の会社しかできない。
それなら、まずは徹底的に信頼するところから始めるべきだ。」
こう考え、制度や仕組みをつくる前に「人を信じること」を最優先したのです。
この発想には衝撃を受けましたし、正直内容を読んで、「いや、信頼しすぎや…」と読みながら心の中でツッコミました…。でも、それが本気だったからこそ、社員たちは応えたのだと思います。
そして、これはまさに私たち社労士にとっても大きな問いを投げかけてきます。
就業規則を整備する、労務トラブルを予防する…。もちろん大切な仕事です。法律を守ることは企業運営の基本であり、トラブルを未然に防ぐためのルールづくりは欠かせません。
でも、「ルールの前に、人を見ること」「信じること」が本当に置き去りになっていないか。
本来あるべき“人と人”の信頼関係を、書面の論理でかき消してしまってはいないか。
そんな自問を突きつけられた気がしました。
また、塚本氏の言う「世間並みの会社にしかならない」という言葉も刺さりました。
平均的で安全で無難なやり方だけでは、本当に魅力ある会社や文化は育たない。
それを証明するかのように、ワコールは“女性のための会社”という確固たる個性と文化を築き上げたのです。
信頼には、当然リスクも伴います。でもそのリスクを取る覚悟があったからこそ、社員との間に“労使”ではなく“同志”のような関係が生まれ、ワコールという企業が唯一無二の存在になっていったのだと思います。
私も、社労士事務所で働く一員として企業を支援する立場にある以上、「当たり前のことをただ当たり前に伝える」だけで終わらず、その会社ならではの個性や価値観、人を信じる文化が育つような関わりをしていきたいと、強く感じました。
また経営の危機にあっても塚本氏は前を向き続けました。給与すらまともに払えない状況の中、社員を集めて「50年計画」を発表したというエピソードは圧巻です。
一見すれば無謀とも思える発言に、社員が「この人が言うなら、本当にそうなるかもしれない」と感じたという話からは、トップとしての信頼と覚悟が伝わってきます。
働く意味を、もう一度問い直す
塚本氏について、本を読み終えて心に残ったのは、「この方は本当に“人に恵まれた”人生だったんだな」ということでした。
でも、それは単に運が良かったわけではありません。
恵まれていたというより、「人を見る目があり、人を信じ抜く力があった」からこそ、人が集まったのだと思います。
そして間違いなく“運”も味方していました。
ただしその運は、待っていて舞い込んできたものではなく、「動き続けていたから」こそ引き寄せられたのだと感じました。
夢を持ち、情熱を燃やし、常に人のため、社会のために動いていたからこそ、運も人も塚本氏のもとに集まったのでしょう。
社員への愛情も並大抵のものではありません。
現場の声に耳を傾け、家族のように寄り添い、ビジョンを高く掲げて道を照らす。
その姿からは、「経営者」としてというより、「人生の先輩」としての懐の深さすら感じました。
そして何より感動したのは、塚本氏が最期まで“自分のために”ではなく、“この国の未来のために”動いていたということです。
私心ではなく、公のために生きる——それは言葉で言うほど簡単ではありません。
けれど塚本氏は、それを本当にやってのけた。そんな人が実際にいたことに、深く胸を打たれました。
戦後、日本がここまで発展してこられたのは、こうした志を持つ人々が、自分の人生を賭けて築いてくれたからこそです。
私たちは、その土台の上に生きています。
けれど今の社会では、「働くこと」が損得で語られる場面が増え、何のために働くのか、本質的な問いが置き去りにされているようにも感じます。
キャリア、収入、効率、権利。大切なことではありますが、それだけでは“働く”という行為の尊さや誇りは生まれないのではないでしょうか。
「このままでいいのだろうか?」
この本を読み終えて、改めて思いました。
私たちは、先人たちの築いてくれたものをちゃんと引き継ぎ、次の世代へつないでいるのだろうか?
これからの日本社会、そして「働くこと」の意味を、もう一度見つめ直していきたい。
そして、私自身も労務を通じて、企業や働く人たちの未来を後押しできるような存在でありたい。
そう強く感じさせてくれる、心が久々に震えた最高の一冊でした。
書籍情報
書名:『ブラジャーで天下をとった男 ― ワコール創業者 塚本幸一』
著者: 北康利
出版社: PHP研究所
★MiraQ会員の皆様へ
この本を読みたいという方は、事務局までお知らせください。